 アイデア
アイデア 観覧車の夢
山の上の観覧車はここからだと指輪みたいで、わたしはその景色がひそかに好きで、稜線に刺した指輪がちんまり光ってるみたいっていうか、小さく見えてる観覧車、さほど遠く...
 アイデア
アイデア  只々日々
只々日々  只々日々
只々日々  只々日々
只々日々  只々日々
只々日々  只々日々
只々日々  只々日々
只々日々 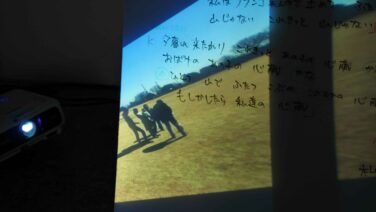 只々日々
只々日々  只々日々
只々日々  只々日々
只々日々